受験生にも役立つ
保護者のための大学受験講座
Epigram003
「まず志望大学を決めなさい」と、言ってはならない!
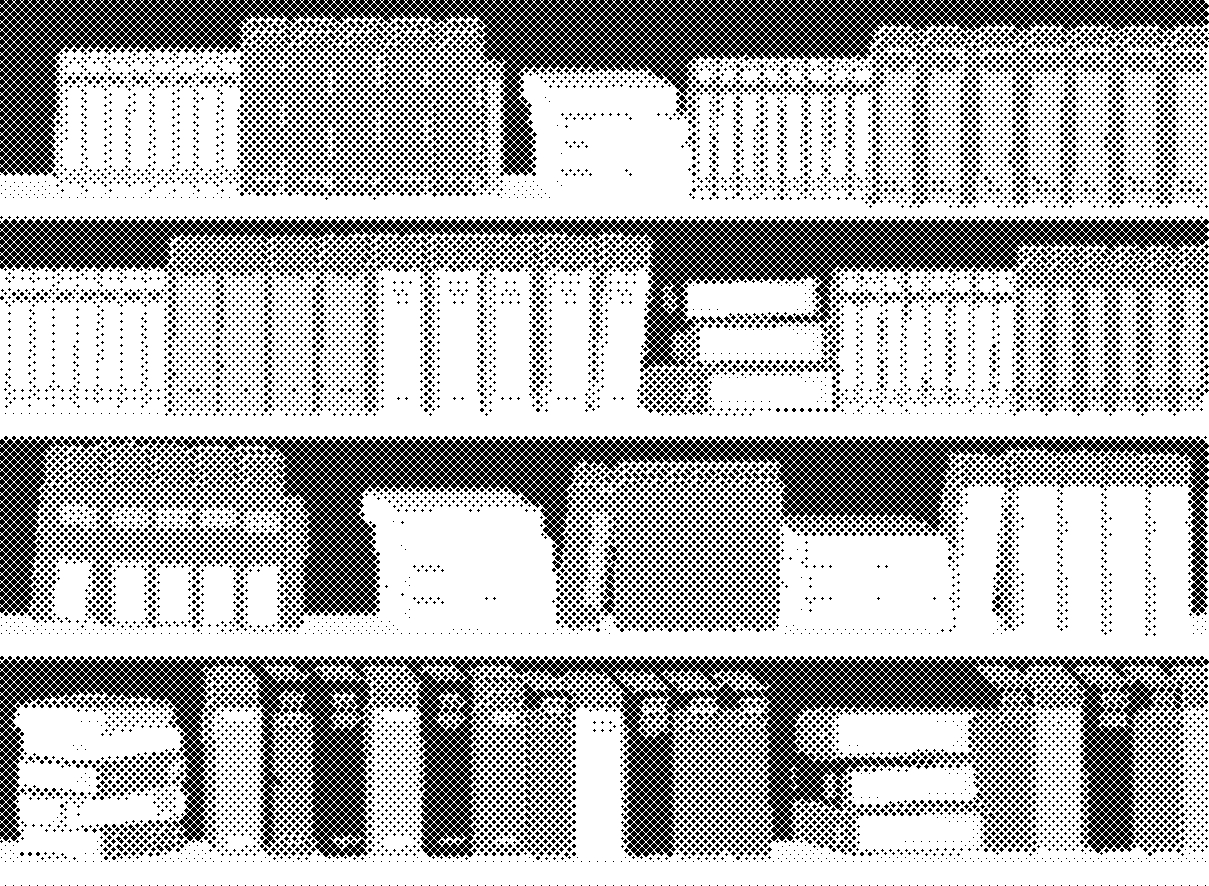
「まずは志望学部を決めなさい」と言わなければなりません。世の中は揺れ動いています。まず決めるべきは学部・学科です。
「どの学部へ行っても同じでしょう」「大学での学習なんて何の役にも立たない、結局はどの学部・学科より、どの大学かがすべててしょ」「学歴は大学名で決まるのでは?」。確かにそうだと思います。皆さんの中で大学を目指した方が、その記憶を辿れば、流石に文系と理系では大幅に受験科目が違うのですから、恐らく中学校の3年生を過ぎた頃には、漠然と自分は理系・文系を選び(註1)、次は大学いや大学名を優先し、それにその時点での自分の成績を加味して、結果として落ち着くべき大学が決まり(註2)、最後に学部が決まっただけなのでは?
確かにこれは言い過ぎかもしれません。積極的に学部・学科を選んだ方もいらっしゃると思います。では、もう少し突っ込んで、伺います、一体、経済学部と商学部と経営学部って、何が違うんでしょう。理学部で学習する基礎化学と工学部にある応用化学とか、やることは何が違うのでしょうか? 確かに“難関”国立大学は学部も割とシンプルで、西洋から明治時代に取り入れた伝統的な学部構成のところが多いですが、国立でも、いや公立なら、いやいやさらに私立ともなると、大学経営の観点から、あるいは学部の統廃合の煽りを受けて、“新設学部”を設立せざるを得なくなり、やたら訳の分からない学部が乱立していると言ってよい。「人間」「環境」「情報」「国際」を学部名に冠している学部は、大抵、それですね(註3)。だから、皆さんが大学を目指された頃とは大学の組織自体が大きく変貌している。
そこで、最初に保護者の方がなすべきことは、大学の合格偏差値やランキングや倍率ではありません。「どこの大学にどういう学部があり、そこでは何が行われているのか」に始まり、「この学部は何をやっていて、何を目指しているのか」「その学部のスタッフにはだれそれがいて、その人は若いけれどその道のトップランナーだ」とか、「ゼミがスゴく充実しているらしい、だから学生指導に定評がある」「研究施設としてこういうものがあり、そこで身につけた知識が将来に活きると評判だ」とか、「卒業が中々に厳しいらしいが、それが就職活動に繋がるとの話だ」とか、そして「さらに学びたい人にはこういう奨学金や留学のルートがある」「トップ大学の大学院に推薦できる強力なパイプがあるらしい」に至るまで。イヤ、簡単ですって、今、流行りのAIに聞いてみてください。ほんの少しの手間で済みますから。
なぜ学部選びが重要か? 長年受験生と接していると、学部選択が間違っている方がたくさんいらっしゃるのです。「それは経済学部ではなくて、法学部だよ」「文学部に心理学科とか社会学科があるのは普通ですね」「教育学部というのは教員になるための学部ではないところも多いゾ」「いや理学部だけが、それをやっているわけではない、農学部もアリ」「それなら工学部の社会システム論の方がよいかも、文系ではなくて、むしろ理系で探してみたら」...。
これは本人の責任というのもあるのですが、実は高校がイケナイ。こういうことをチャントやっている高校さんがないとは申しませんが、極めて少ないことは間違いない。学習指導の前に、校内成績と偏差値で輪切りにする進路指導の前に、そして何よりも学校推薦をチラつかせる前に、なすべきは語の勝(すぐ)れた意味における“進路指導”だと思うのですが、これがなってない。そんな現状の許で、「君たちの可能性は無限だ」「君の未来は開かれている」なんぞと言われたって、鼻白む(はなじろむ)ばかりで、薄寒い(うそさむい)。
そこで皆さん、保護者の登場です。学校の先生方より、遙かに社会の中で現実と対峙してきた皆さんこそ、お子さんの学部・学科適性を語る資格と権利があるはずです。ここからお子さんとの対話を切り開きましょうよ。このような地道な作業がお子さんとの連帯に繋がるのです。
結論、「まず志望大学を決めなさい」ではなくて、「まず志望学部を決めなさい」と言ってみる、そして「少なからぬ情報を持ち合わせているよ」と付け足してみましょう。さて、それが見えたらいよいよ大学選びです。それはまた次の機会に。
(註1) 実は本当はもう一回ありますね、高校1年生の秋くらいに、「あ、違った、理系じゃないな、文系だ」というヤマーもしかしたらタニが。これに纏わる話は、近々メンバーサイトの方で書きます。
(註2) 実の所はもう一つ、どの“場所”へ行くのか、というのがありますが、この“大問題”についてはここではなくて、看板ページで準備中です。
(註3) 大学の1・2年次に、まず教養学部においてリベラル・アーツを身につけ、それから改めて専門学部へ進むという大学の理念が“外圧”で崩壊させられると同時に、大学自らがその理念を放棄して自壊させた結果...、なんてここで書くと、お叱りを受けそうですが、そのような学部名の元を辿ると、昔の教養学部の組織改編のナレの果て、なんてことが往々にしてあるのです。そう言えば、随分前に出た本なのに、米津玄師さんが紹介した途端に、バカ売れして、出版社の中の人が驚いたと言われる本の題名は、竹内洋著『教養主義の没落』 (中央公論新社 2003)でしたね。
